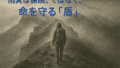「リーダーが下す最も難しい決断は、山頂を目前にした撤退の判断ではありません。それは、まだ家を出る前、あるいは登山口に立つ前に下される、『中止』または『変更』の決断です」

皆さん、こんにちは。MA-SANです。
計画を中止したり、楽しみにしていたコースを変更したりするのは、非常に勇気がいることです。参加者をがっかりさせてしまうのではないか、自分の判断は過剰ではないか…そんなリーダー自身の「心の葛藤」が、時に合理的な判断を曇らせ、パーティー全体を危険に晒すことがあります。
今回は、私が実際に相談を受けたあるランニングチームの実例を基に、天候やコンディションを理由とした「勇気ある判断」が、いかにして参加者の命を守るのかについてお話しします。
事例:「過剰な配慮」と「最善の判断」の狭間で
私がアドバイザーとして関わっている、とあるランニングチームでの出来事です。このチームの主催者は昔から気心が知れており、お互いに何かあれば相談する間柄です。安全への意識が高く、自分たちのクライアントに、何か大きな事故が起こらないように、常に(臆病な位)気にしています。
ある週末、彼らは少し難易度の高い山域でのトレイルランニングイベントを計画していました。しかし、天気予報はイベント前日から当日の午前中にかけて、かなりの降雨を示していました。
イベント前日の夜、主催者から私の元に一本の電話が入りました。
「MA-SAN、相談があります。明日のコースですが、この雨で登山道がかなりぬかるんでいると思うんです。先日も事故が起きたとお聞きしましたし、このまま強行しても大丈夫でしょうか?それとも、コースを変更すべきでしょうか?」
主催者さんの声には、迷いとプレッシャーが滲んでいました。計画通り実行することは、おそらく可能でした。しかし、彼はいくつかの懸念を抱えていました。
「参加者名簿を改めて見ると、数名、まだトレイルランニングの経験が浅い方がいるんです。彼らが滑りやすい急な下りで、対応できるかどうか…」
これが、リーダーとして最も重要な視点でした。自分の判断基準を、パーティーの中で最も経験の浅い、あるいは体力の劣る「最弱のリンク」に置くこと。この主催者は、それができていました。
私たちは、いくつかの選択肢を検討しました。
- 計画通り決行する: 経験の浅い参加者には、特に慎重に行動するよう注意喚起する。しかし、リスクは残る。
- イベント自体を中止する: 最も安全だが、遠方から来る参加者の気持ちを考えると、避けたい選択。
- コースを変更する: より安全で、悪天候でも比較的リスクの低いルートに切り替える。
私たちは、3つ目の「コース変更」を選択しました。今回のコースは急峻な岩場や滑りやすい下りが少ない、緩やかなトレッキングルートを基にした代替コースを設計しました。物足りなさを感じる参加者もいるかもしれないと考え、走力がある方達は最初に走る距離を少し長めに設定することで、走りごたえのあるプランに調整しました。
そして翌日。案の定、変更後のコースですら、道は非常に滑りやすいコンディションでした。そして、実際に事故は起きてしまいました。一人の参加者が、ぬかるみで足を滑らせ転倒し、足首を捻挫してしまったのです。
しかし、ここからの対応が、「勇気ある判断」の正しさを見事に証明しました。
- アクセスの容易さ: 変更後のコースは林道に近く、車がアクセスできる場所が多かったため、事前に待機させていたサポートカーがすぐに現場近くまで来ることができました。
- 迅速な連絡体制: 電波状況も比較的良好で、リーダーとサポート部隊の連携がスムーズに行えました。
- 最小限の被害: 負傷者はすぐに車で病院へ向かうことができ、他のメンバーも安全に下山を完了。大事には至りませんでした。
もし、当初の計画通り、より奥深く、エスケープルートの少ない山域で同じ事故が起きていたらどうなっていたでしょう?救助隊の要請、数時間に及ぶ搬送、負傷者の低体温症リスク…事態は間違いなく、深刻化していました。この主催者の「勇気ある判断」は、起こってしまった事故を、「遭難」ではなく「軽微なアクシデント」で食い止めたのです。
遭難の分析:「中止」をためらうリーダーの心理
なぜ、多くのリーダーが悪天候の中、決行をためらってしまうのでしょうか。そこには、いくつかの心理的な罠が存在します。
- 1. サンクコスト効果(埋没費用): 「ここまで時間と労力をかけて準備してきたのだから、今さら中止にはできない」という心理です。過去に費やしたコストに囚われ、未来のリスクを過小評価してしまいます。
- 2. 同調圧力と期待への恐怖: 「みんなが楽しみにしているのに、自分が水を差すわけにはいかない」「中止したら、がっかりさせてしまう、責められるかもしれない」という、参加者からの見えざるプレッシャーです。
- 3. 正常性バイアスと楽観的希望: 「天気予報は外れるかもしれない」「行ってみたら、意外と大したことないかもしれない」という、根拠のない希望的観測です。危険な兆候を「自分に都合よく」解釈しようとします。
- 4. リーダーとしてのプライド: 「中止や変更は、自分の計画ミスや弱さの表れだ」という、誤った自尊心です。
これらの心理は、リーダーを一人の人として追い詰め、冷静な判断を奪います。だからこそ、感情やその場の空気に流されない、「客観的な判断基準」を事前に持っておくことが不可欠なのです。
教訓:勇気ある判断を下すための「ジャッジメント・コード」
天候はコントロールできません。しかし、その天候に対してどう行動するかは、リーダーであるあなたがコントロールできます。感情論や精神論を排し、冷静な判断を下すための3つの行動規範です。
CODE 1:リスク評価は「最も経験の浅い参加者」を基準にする
パーティーの行動基準は、最も体力があり経験豊富なメンバーに合わせてはいけません。必ず、最も経験が浅く、体力がなく、装備に不安のあるメンバーが、予期せぬトラブルを含めて安全に行動できるかを基準にしてください。「あの人がいるから、このコースは止めよう」という判断ができることが、優れたリーダーの証です。
CODE 2:判断基準を「事前に」明文化し、共有する
「中止」や「コース変更」の判断を、当日の感情やその場の雰囲気で決めてはいけません。事前に、客観的な基準を文章として定め、参加者全員に共有しておくのです。
(例)
- 中止基準: 前日17時時点で、現地の気象警報(大雨、洪水、暴風など)が発令されている場合。
- コース変更基準: 24時間以内の降水量が50mmを超えた場合、または当日の風速予報が山頂で15m/sを超える場合は、プランBのコースに変更する。
このように基準を明文化しておくことで、リーダーは心理的プレッシャーから解放され、参加者もその判断に納得しやすくなります。「ルールに従ったまで」と、客観的な事実に基づいて決断できるのです。
CODE 3:代替案(プランB)を常に用意し、それを「残念賞」にしない
「中止」というゼロの選択肢だけでなく、常に代替案である「プランB」を用意しておくことが、リーダーの力量です。今回の事例のように、技術的な難易度は低いが、別の魅力(景色が良い、距離が長く走りごたえがあるなど)を持つコースを準備しておきましょう。そして、プランBを「格下の残念なコース」ではなく、「今日のコンディションで最も楽しめる、賢明な選択肢」として、ポジティブに参加者に提示するのです。これにより、参加者の満足度を保ちながら、安全を確保することができます。
最後に
山の計画において、天候の悪化は「想定外」の出来事ではありません。それは、必ず起こりうる「想定内」のリスクです。そのリスクに対して、いかに賢明な判断を下せるか。リーダーの真価は、そこにこそ問われます。
計画を変更する勇気、中止を決断する勇気。それは、決して「逃げ」や「失敗」ではありません。参加者全員の未来の山行を守るための、最も尊い「前進」なのです。
山の神様は、時に「来るな」というサインを送ります。その声に耳を傾ける勇気こそ、リーダーが持つべき最大の資質なのですから。