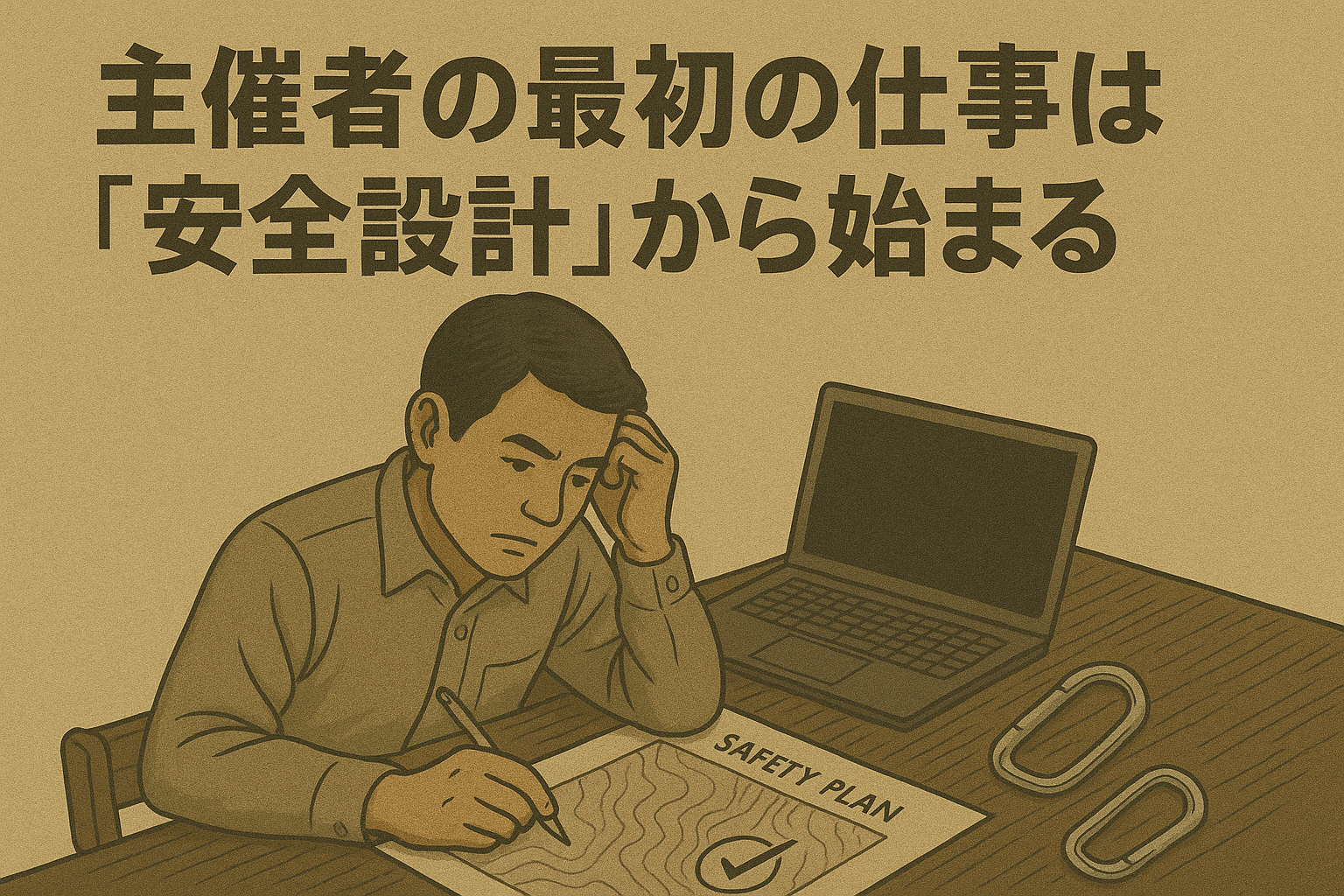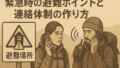山のイベントは、非日常の楽しさに満ちています。
しかしその裏側で、主催者は「日常に帰らせる責任」を負っています。
どんなに素晴らしいコースを設定しても、安全が確保されていなければ、それは“事故待ちの企画”になってしまいます。
イベントを成功させたいと願うなら、まず考えるべきは「どうすれば誰も傷つかずに帰れるか」。
楽しいより先に、帰れること。その仕組みを作るのが、主催者としての出発点です。
事例:予定ルートの短縮ができず、事故に発展した事案
2022年秋、とあるトレイルランナー達が10名規模で行った練習会。
コースは40kmで標高差3000mを含む上級者向けのある大会の前半ルート。
天気予報は曇りのち雨、午後からの降水確率は50%でした。
走力の高い人の集まりだったのでリーダーは「明るいうちに下山できるはず」として予定を変更せず、そのまま実施。
ところが登山口の集合時点で既に雲行きが怪しく、予想よりも早く雨が降り始めました。
ルートにはエスケープルート(短縮ルート)が1か所だけありましたが、主催者自身がそのバスが運行しているエスケープ場所を把握しておらず、他の参加者も、走力が高いだけで、どの程度の距離・時間で降りられるのか把握していなかったのです。
結果、予定ルートを強行。
後半で足が止まったメンバーが低体温と脱水を起こし、1名が歩行不能となり、通報。
雨ではヘリは飛ばず、救助隊とともに数時間の搬送が必要となりました。
安全設計とは「起こらないこと」にも準備すること
イベントを「どのように楽しくするか」「どれだけ走れるか」という視点で設計する主催者は多いですが、
山で人を動かすなら、
“起きてほしくないこと”への想像力と準備
が必要です。
安全設計とは、事前に「どこで」「誰が」「何に困るか」を想像し、そのための手を打っておくこと。
・予備ルートがあるか
・エスケープルートの実測データがあるか
・携帯が通じる場所が明確か
・急変時に引き返す判断を、事前に共有しているか
エスケープルート、通信エリア、下見──地味だけど必須な準備
地図に線を引くだけでは安全は担保されません。
実際に主催者自身がルートを歩き、「時間がかかる場所」「迷いやすい分岐」「圏外エリア」を把握する必要があります。
とくに初めてのコースであれば、数回に分けて試走し、天候の違いによる変化も確認しておくべきです。
また、緊急時の通信手段があるかどうかで生死が分かれる場面もあります。
圏外の場所とその脱出経路、スタッフ間の無線やメッセージ手段の確認も、重要な安全設計の一部です。
安全を整えたイベントには、安心が宿る
「楽しかった」は、何も起きなかったことの裏返しです。
しかし、その“何も起きなかった”は偶然ではなく、主催者が細かく整えてくれたおかげ。
参加者の多くはそのありがたみに気づかないかもしれません。けれど、それで良いのです。
何も起こさない努力こそが、信頼される主催者の条件です。
まとめ:楽しいイベントは、地味な準備の上に成り立つ
誰もが楽しめるイベントをつくりたい。
だからこそ、まずは事故が起こらないように設計する。
これは主催者の責任であると同時に、参加者からの信頼を得るための最短ルートでもあります。
目立つ演出や記念撮影よりも前に、安全設計という「見えない準備」を積むこと。
それが、主催者としての第一歩であり、最も価値ある裏方の仕事です。