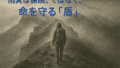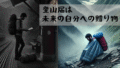「山で最も危険な瞬間は、険しい岩場や吹雪の稜線だとは限らない。むしろ、ゴールまであと少し、という気の緩みが生まれる瞬間にこそ、遭難への扉は音もなく開かれる」

山岳救助の現場に長く身を置いていると、そんな皮肉な現実を何度も目の当たりにします。皆さん、こんにちは。MA-SANです。
今回は、多くの人が陥りがちな「心の罠」について、具体的な事例をもとにお話しします。特に、経験者であればあるほど「自分は大丈夫」と思い込みがちな、この危険な心理状態。これは決して他人事ではありません。今回取り上げるのは、都心からも近く、多くのハイカーに親しまれている奥多摩の、比較的平易なトレッキングコースで起きた遭難事例です。
事例:奥多摩昔道で起きた、ベテラン登山者の遭難
その日、70代の女性2人組は、奥多摩の「むかし道」を歩いていました。彼女たちは若い頃に本格的な登山を経験し、今はその知識と経験を活かして、穏やかな自然の中をゆっくりと散策することを楽しみにしている、いわばベテランハイカーです。
「むかし道」は、その名の通り、かつて集落を結んでいた生活道。激しいアップダウンも少なく、道標も整備されており、登山というよりはトレッキングやハイキングといった方がしっくりくる、明瞭なコースです。
天候にも恵まれ、2人は談笑しながら順調に歩を進めていました。ゴール地点である「境」集落まで、あとわずか。心地よい疲労感と共に、「今日も無事に楽しく歩けたね」と、安堵の気持ちが芽生え始めた、まさにその時でした。
正規ルートから分岐する、細い道が目に入ります。そこには古い看板がありました。今はもう使われていない「多摩駅」という文字が、かろうじて読み取れます。正規ルートの標識を見落としたのか、あるいは「こちらも行けるのかもしれない」という淡い期待を抱いたのか、2人はその細い道へと足を踏み入れてしまいました。
そこは、かつて「城(じょう)」と呼ばれた集落跡へと続く古道でした。
歩き始めてすぐに、2人は異変に気づきます。今までとは明らかに違う、荒れた道。踏み跡は不明瞭になり、路肩は崩れかけています。

後日、救助された彼女たちは、口を揃えてこう言いました。
「おかしいとは、すぐに思ったんです。絶対に道を間違えている、と」
しかし、2人は引き返しませんでした。なぜか。
一人が「おかしい」と感じていても、隣を歩く友人は何も言わずに前へ進んでいる。
「もしかしたら、この道で合っていると確信しているのかもしれない。ここで『間違っているのでは?』と水を差すのは悪いかな…」
もう一人も、同じことを考えていました。
「道は悪いけれど、相手は経験豊富な人。何も言わないということは、何か考えがあるのかもしれない。私一人が騒ぐことでもないか…」
お互いが、相手は「大丈夫」だと思っている、と忖度してしまったのです。そして、こうも思いました。
「ここまで結構歩いてきてしまったし、今さら戻るのも大変だ」
この、「おかしい」という確信と、「引き返す」という行動の間には、見えない壁が存在します。この壁こそが、今回解説する「正常性バイアス」と「ゴール目前の油断」という、恐ろしい心の罠なのです。
結果、2人はどんどん山の奥深くへと迷い込み、ついには道が崩落している箇所で一人が足を滑らせ、約5メートル滑落。右足を骨折するという大怪我を負ってしまいました。
幸運だったのは、その場所が携帯電話の電波が奇跡的に届くエリアだったことです。すぐに救助要請ができ、我々救助隊が出動。日没が迫る中、なんとかその日のうちに救助を完了できましたが、もし電波がなければ事態はさらに深刻化していたでしょう。夜間の山中、動けない仲間を抱え、寒さと不安の中で一夜を明かす…それは命に関わる事態に直結します。
救助後、彼女たちは「本当に怖かった。おかしいと思った時に、なぜ一言『引き返そう』と言えなかったのか…」と、深く後悔していました。
遭難の分析:彼女たちを支配した「3つの心の罠」
この遭難は、体力の限界や装備の不備が直接の原因ではありません。ベテランである彼女たちの心の中に巣食った、3つの「罠」が原因です。
1. 正常性バイアス:「きっと大丈夫」という根拠のない思い込み
正常性バイアスとは、多少の異常事態が起きても、それを「正常の範囲内」と捉え、心の平穏を保とうとする人間の心理的な働きです。災害心理学などでよく使われる言葉ですが、これは登山中に頻繁に現れます。
- 「いつもより少し天気が悪いけど、まあ大丈夫だろう」
- 「道が少し荒れているけど、すぐ元に戻るだろう」
- 「体調が少し優れないけど、歩いているうちに治るだろう」
今回のケースでは、「コースは簡単」「自分たちはベテラン」という前提が、このバイアスを強力に後押ししました。「おかしい」という明確なサイン(荒れた道)を目の前にしながらも、「まさか、この程度のコースで遭難するはずがない」という思い込みが、危険信号を無視させてしまったのです。
救助現場で遭難者から話を聞くと、この「大丈夫だと思った」という言葉を本当によく耳にします。それは嘘や言い訳ではなく、その瞬間は本気でそう思い込んでいるのです。人間の脳は、不安や恐怖というストレスから逃れるために、無意識に「危険ではない」という物語を作り上げてしまうことを知っておいてください。
2. ゴール目前の油断:「あと少し」が判断を鈍らせる
これは、登山の世界で「サミットフィーバー」と呼ばれる心理状態の亜種です。山頂(サミット)を目前にすると、それまでの苦労が報われるという期待感から正常な判断ができなくなり、天候の悪化や体調不良を無視して突き進んでしまう現象を指します。
今回のケースは山頂ではありませんが、「ゴール(境集落)まであと少し」という状況が、全く同じ心理状態を生み出しました。
「ゴールはすぐそこだ。今さら引き返すのは時間と労力の無駄だ」
「この道を進んでも、どこかで合流できるだろう」
ゴールが近いという安堵感は、リスクに対する感度を著しく低下させます。救急救命士の観点から言えば、これは一日の行動の終盤で、体力的にも精神的にも疲労がピークに達している時間帯と重なるため、危険度は倍増します。疲労は、筋肉だけでなく脳の働きも鈍らせます。複雑な判断を下すための認知機能が低下しているところに、「ゴールが近い」という強い誘引が加わることで、合理的な判断が下せなくなるのです。
3. 同調圧力とコミュニケーション不足:「言わなくても分かる」の幻想
そして、今回の遭難の決定打となったのが、この3つ目の罠です。2人とも「おかしい」と思っていたにも関わらず、その一言が言えなかった。
- 「相手に気を遣ってしまう」
- 「和を乱したくない」
- 「自分の判断に自信がない」
こうした気持ちは、特に日本人には強く見られる傾向かもしれません。しかし、山においては、この「阿吽の呼吸」や「忖度」は命取りになります。あなたの隣を歩いているパートナーは、超能力者ではありません。「言わなくても分かるだろう」は、ただの幻想です。
むしろ、逆です。山では、「おかしい」と思ったことを口に出すのが、パートナーに対する最大の思いやりであり、パーティーとしての義務なのです。もし、あなたの感じた「違和感」が杞憂に終わったとしても、それはそれで良いのです。確認作業を一つ経たことで、パーティーの安全性は確実に向上します。何も失うものはありません。
教訓:心の罠から命を守るための「THE MOUNTAIN CODE」
では、どうすればこのような心の罠から逃れられるのでしょうか。ここに、あなたが守るべき3つの行動規範を提案します。
CODE 1:違和感を声に出すことを「パーティーのルール」にする
登山開始前に、仲間とこう約束してください。「少しでも『あれ?』『おかしいな』と感じたら、どんな些細なことでも、必ず声に出して共有しよう」と。これをパーティーの絶対的なルールとするのです。違和感を口にすることは、和を乱す行為ではなく、ルールを守る素晴らしい行為である、という共通認識を作っておくことが極めて重要です。
CODE 2:「10分ルールの徹底」で前進を止める勇気を持つ
「道が怪しい」と感じてから、10分以上進んでも状況が改善しない、あるいは確信が持てない場合、行動の選択肢はただ一つ。「最後に確信が持てた場所まで、即座に引き返す」。これを行動の原則としてください。不確かな道へ進むのは、コンパスも持たずに霧の中へ飛び込むのと同じです。引き返す勇気こそ、ベテランの証です。
CODE 3:登山のゴールを「無事に家に帰ること」に再設定する
山頂に立つことや、コースを歩き切ることは、登山の目的ではあっても、最終ゴールではありません。真のゴールは「無事に自宅の玄関を開けること」。この意識を常に持ってください。そうすれば、「引き返す」という判断は「失敗」ではなく、「ゴール達成のための、最も賢明なリスク管理」に変わります。このマインドセットの転換が、あなたを正常性バイアスやサミットフィーバーの呪縛から解き放ってくれるはずです。
今回の奥多摩の事例は、決して特別なものではありません。日本中のあらゆる山で、今日も誰かの心の中で同じような葛藤が起きています。
あなたの経験、あなたの体力、あなたの装備、それらはもちろん重要です。しかし、それらを使いこなすあなたの「心」が罠に陥ってしまえば、全ては無力化します。
地図を読む前に、まず自分の心を読んでください。
天候を気にするように、自分の心の状態を気にしてください。
それこそが、山で死なないための、最も重要な基礎知識なのですから。