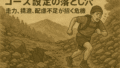ガイドツアーやトレランの練習会、仲間内のハイキング…あなたが誰かを山へ案内する時、その安全設計は本当に万全ですか?
「参加者の自己責任だから」
その便利な言葉の裏で、主催者として果たすべき“責任”から目を背けてはいませんか?
一つの事故は、参加者の人生だけでなく、主催者として築き上げてきた信頼の全てを奪い去ります。
今回は、参加者の命とあなたの未来を守るための「遭難ゼロ設計」について、厳しい現実の事例をもとにお話しします。
事例:戻ってこなかった、最後尾の男性
ある日、初心者向けのトレッキング講習会が開かれました。
参加者は5名。主催者は、難しいコースではないこと、そして少人数であることを理由に、特に最後尾を管理する「スイーパー」を配置せずにイベントをスタートさせました。
一番後ろを歩いていたのは、運動不足解消のために登山を始めたばかりの50代の男性。彼は「少しペースが速いな」と感じながらも、周りに迷惑をかけまいと必死に皆のペースについていきました。
最終目的地である山中の避難小屋に到着し、下山準備をしていた時でした。突然、彼の足が激しく攣ってしまったのです。皆は次々と小屋から出発していきます。「待ってくれ」と言いたいものの、皆の足を引っ張りたくない一心で、彼は痛みに耐えながら急いで支度をしようと試みます。しかし、足の攣りは一向に収まりません。
一方、彼が小屋で苦しんでいるとは知らず、ガイドが率いる本隊は下山を開始していました。「あとは下るだけ」という気の緩みもあり、主催者が最後尾の男性がいないことに気づいたのは、歩き始めてから実に30分も経ってからでした。
なぜ救助は遅れたのか?主催者の致命的な判断ミス
この事例で、なぜ男性は一晩も避難小屋に取り残され、救助が大幅に遅れてしまったのでしょうか。そこには、主催者側の明確な判断ミスがいくつも重なっていました。
人員配置の欠如と現状把握の遅れ
最大の過ちは、最後尾を確認するスイーパーを配置しなかったことです。これにより、最後尾の状況が全く把握できず、男性が30分もの間いなくなっていることにすら気づけませんでした。
安易な楽観視と希望的観測
男性と連絡が取れない状況にも関わらず、主催者は「彼はコミュニケーションをあまり取る方ではなかったから、別のルートで先に下山したのかもしれない」という、何の根拠もない希望的観測にすがってしまいました。この楽観視が、警察への迅速な通報を妨げ、貴重な時間を失わせたのです。
不十分な装備計画
参加者たちはヘッドライトを持っていませんでした。日が暮れた後、主催者自身が捜索に戻ることも困難な状況でした。また、携帯電話が圏外になることを想定した通信手段(無線機など)も確保されていませんでした。
結果、主催者は残りの4人を安全に下山させることを優先し、要救助者への対応が後手に回りました。通報は翌朝、心配した家族から主催者への連絡がきっかけとなり、あまりにも遅すぎるものとなったのです。男性は幸いにも無事でしたが、一歩間違えれば命に関わる事態でした。
「遭難ゼロ」を実現する3つの仕組み
事故は、個人の体力や判断ミスだけで起こるのではありません。むしろ、その多くは「運営設計の甘さ」という、主催者側の責任領域で発生します。「少人数だから大丈夫」「経験者ばかりだから問題ない」――そのような思い込みこそが、事故を呼び込むのです。
「遭難ゼロ」は、決して運や偶然で達成されるものではありません。それは、主催者が意図して作り上げる「仕組み」によって実現されるのです。
仕組み1:スイーパー(最後尾)の配置
どんなに少人数のイベントでも、必ず最後尾を歩き、全体のペースや参加者の様子を確認する「スイーパー」を配置してください。スイーパーは、隊列の「しんがり」を守る最後の砦です。彼らがいることで初めて、主催者は「誰一人、はぐれていない」という確信を得られるのです。
仕組み2:確実な点呼と通信計画の徹底
分岐点、休憩ポイント、山頂など、行程の節目では必ず全員の点呼を行ってください。そして、携帯電話が通じないことを前提とした通信計画(無線機や衛星電話の活用)を立て、リーダーとスイーパーが常に連携できる体制を築くことが不可欠です.
仕組み3:信頼をコストで測らない覚悟
安全管理にはコストがかかります。スイーパーを増員すれば、人件費は増えるでしょう。しかし、そのコストを惜しんだ結果、一つの事故が起これば、イベントの評判、主催者としての信頼、そして何より参加者の命という、お金では決して取り戻せないものを失います。参加者を無事に家に帰すことこそが最大の利益であり、そのための投資は最も価値あるものなのです。
まとめ:【CODE 0-1】イベントの成功とは、参加者全員の無事な帰宅である
山では「自己責任」という言葉がよく使われます。しかし、イベントの主催者は、その言葉を免罪符にしてはなりません。安全なフィールドを設計し、ルールを定め、参加者全員を無事に家まで送り届けるまでが、主催者の果たすべき「責任」です。
CODE 0-1: イベント主催者は、参加者の「自己責任」という言葉に逃げてはならない。安全なフィールドとルールを設計し、参加者全員を無事に帰宅させるまでが、主催者の“責任”である。
この掟を胸に刻み、以下の行動を徹底してください。
CODE 1:【設計】最悪を想定し、人員を配置せよ。
「大丈夫だろう」は、思考停止の合図です。どんなに簡単なコースでも、必ず最後尾を管理するスイーパーを配置し、通信計画を立ててください。安全管理のコストは、信頼を守るための必要経費です。
CODE 2:【把握】点呼と連携で、常に全員の位置を把握せよ。
隊列は伸び、離れるものだと心得てください。休憩や分岐のたびに必ず点呼を行い、リーダーとスイーパーは常に連携を取り、全員が「ここにいる」ことを確認し続けてください。一人の逸脱が、グループ全体を危険に晒します。
CODE 3:【決断】異変には即座に対応し、希望的観測を捨てよ。
「あれ?」という小さな違和感こそ、重大事故への最初のサインです。即座に隊列を止め、状況確認を最優先してください。通報や捜索の判断を、「〜かもしれない」という希望的観測で決して遅らせてはいけません。あなたの迅速な決断が、命を救います。