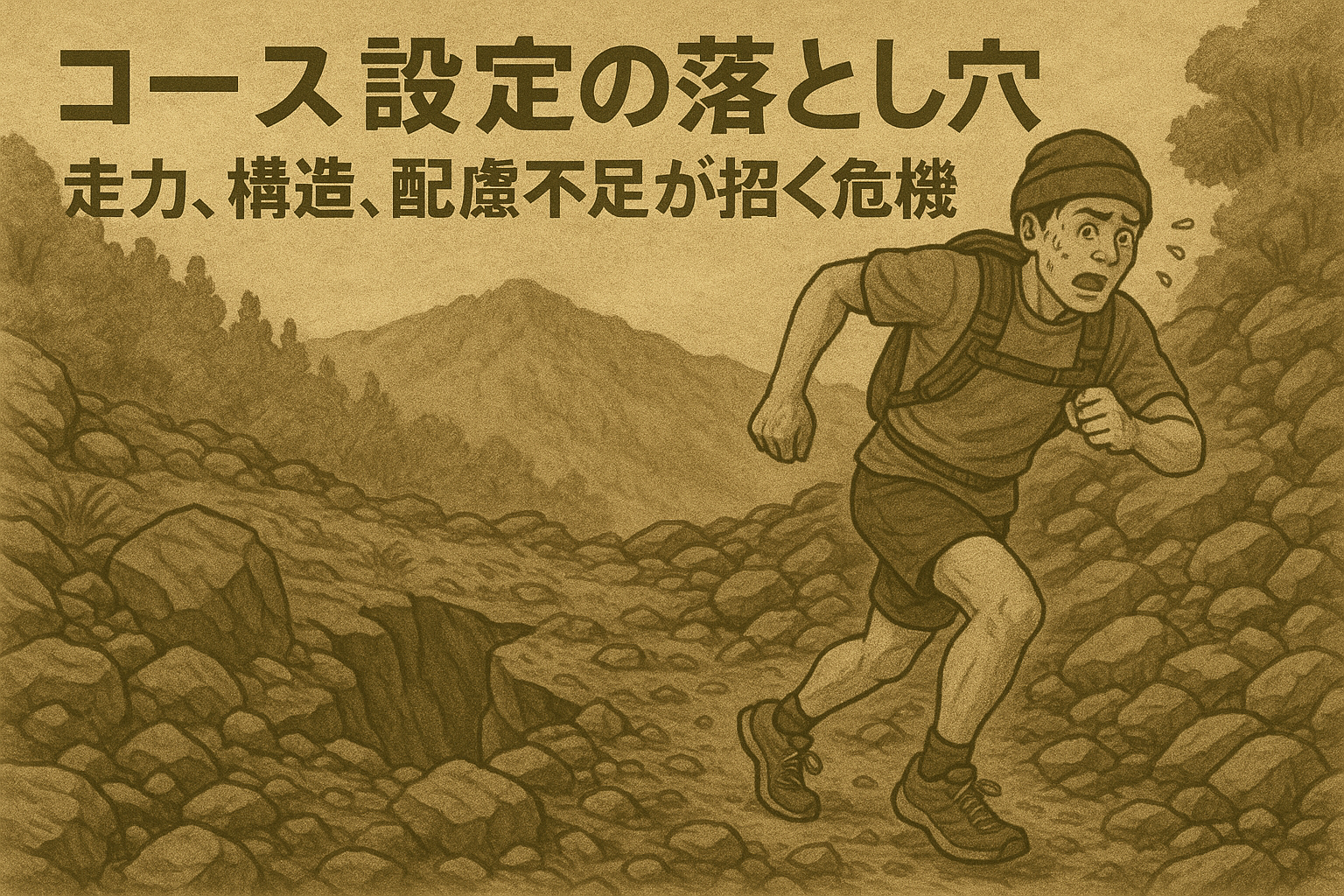イベントのルートを引く時、あなたは何を基準にしていますか? 多くの主催者が、まず「距離」と「累積標高」という数字を思い浮かべるかもしれません。
しかし、ルートとは単なる地図上の線ではありません。そこは、体力差、心の動き、そして人間の生理現象という、様々なドラマが繰り広げられる舞台なのです。
参加者の「人の流れ」と「気持ちの流れ」を想像せずに引かれたルートは、時に災害の設計図になり得ます。今回は、経験豊富なリーダーほど陥りやすい、コース設定の落とし穴についてお話しします。
走力差を無視した「一本道」の危険性
イベントや練習会には、様々な体力、異なる経験を持つ参加者が集まります。この時、最も速い人と最も遅い人を、同じ一本道のコースで同時にスタートさせたら何が起きるでしょうか?
多くの場合、速い人たちはエネルギーを持て余し、遅い人たちは「迷惑をかけてはいけない」というプレッシャーと焦りで疲労困憊になります。特に主催者自身が速いペースで先頭を走ってしまうと、後方の状況が全く見えなくなり、誰かが遅れていること、体調を崩していることに気づくのが大幅に遅れます。これは、リスク管理の崩壊です。
この問題を解決するには、コース設計に「工夫」が必要です。例えば、序盤の走りやすい林道などで、速い人たちにだけ往復や周回コースを追加で走ってもらうのです。これにより、速い人たちは満足のいく運動量を確保でき、遅い人たちとの時間差が自然と調整されます。そして、後から速いグループが本隊に合流する形にすれば、全員で一体感を持ちながらゴールを目指す、という理想的な展開を作ることが可能なのです。
「一度下山」がモチベーションを破壊する心理的な罠
コースの中盤で、駅や麓の登山口など「ゴール感のある場所」に一度下ろしてしまう構成は、非常に大きな心理的な罠をはらんでいます。
人間は本能的に、標高の高い場所から低い場所へ、特に山の中から人の営みがある麓へ降りてくると、「終わった」「助かった」と無意識に感じてしまいます。一度この「下山モード」に入ってしまった心と体を、再び登りへと向かわせるのは至難の業です。特に体力がぎりぎりの参加者にとっては、一度切れた緊張の糸を再び張り直すのは、ほとんど不可能です。
この状態での再入山は、集中力が散漫になり、転倒、道迷い、体調不良のリスクを急激に高めます。これは音楽で言えば、感動的なフィナーレを迎えた後にもう一度、本編が始まってしまうようなもの。コースの物語は、下山をゴールとセットで設計するのが鉄則です。もしどうしてもアップダウンが必要な場合は、参加者の気持ちをリセットさせるための明確な声かけ、特別な補給、そして「ここからが第二ステージです」といった意識の切り替えを促す演出が不可欠になります。
生理現象の軽視が生む「離脱リスク」
特に女性参加者が多いイベントで、トイレの場所を考慮せずにルート設定をしてしまうのは、主催者として配慮が欠けていると言わざるを得ません。
ルート上にトイレが確保できないと、「トイレに行くために一時的に列を離れる」という行動が生まれます。この「単独での離脱」こそが、道迷いや滑落事故の非常に大きなきっかけになるのです。世界的に有名な女性登山家でさえ、男性パートナーと行動中に少し離れて用を足そうとした際に滑落して命を落とした事故は、このリスクの重大さを物語っています。
対策はシンプルです。最低でも10kmに1回、あるいは2〜3時間に1回は、トイレのある場所(山小屋、公園、公共施設など)を通過するルートを設計すること。そして、そのタイミングで休憩や補給をセットで行うことで、参加者は安心して列を離れることなく生理現象に対応できます。また、事前の説明で「次のトイレは〇〇です。ここで長めに休憩を取るので、必ず済ませておきましょう」とアナウンスするだけで、参加者の安心感は大きく変わるのです。
まとめ:【CODE 0-2】優れたルートとは、全員が無事に帰れる道のことである
どんなに安全に見える道でも、「誰が、どう動き、どこで気持ちが切れるか」まで想像できなければ、それは落とし穴だらけの危険なルートになり得ます。コース設定とは、単に地図に線を引く作業ではありません。体力、心理、生理現象という「人間の流れ」を読み解き、全員を安全なゴールへと導く設計そのものです。
なぜそう言い切れるかって? 私が15年間の山岳救助で見てきた遭難事例のほとんどが、このどれかの配慮不足に起因しているからです。
CODE 0-2: コース設定とは、地図に線を引く作業ではない。体力、心理、生理現象という「人間の流れ」を読み解き、安全なゴールへと導く設計そのものである。
CODE 1:【体力差への配慮】一本道ではなく、「周回」や「往復」でペースを吸収せよ。
参加者全員を一本の線で管理しようとしてはいけません。序盤にループや往復コースを設けるなどして、意図的に「遊び」を作り、速い人のエネルギーを発散させ、グループ全体のペースを自然に調整する工夫をしてください。
CODE 2:【心理への配慮】物語の「起承転結」を意識し、モチベーションの崖を作るな。
ルートには一つの物語があります。途中で「下山」というフィナーレを迎えてしまうと、参加者の心は折れてしまいます。下りは必ずゴールとセットで設計し、参加者のモチベーションが途切れない流れを意識してください。
CODE 3:【生理現象への配慮】人間の基本的ニーズを、計画の最優先事項とせよ。
トイレや水の確保は、ルート設定における最優先事項です。これらは「あれば良い」ものではなく、「なくてはならない」インフラです。人間の生理的欲求を計画に織り込むことは、参加者への敬意であり、リスクを未然に防ぐ最も確実な方法です。