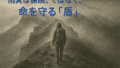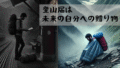今回ご紹介するのは、「マラソン歴10年超」の男性が、初めて参加したトレイルランの大会で自信をつけ、そのまま仲間を誘って再び山に入った結果、命を落としてしまったという事例です。
「走力がある」「体力に自信がある」──そんな思い込みが、山では裏目に出ることがあります。
大会の高揚感が冷めやらぬまま、
リスクの見積もりが甘くなる。
装備や地形への理解が浅いまま、他者を連れていく。
これは、ロードランナーに限らず、
すべてのトレイル初心者が直面する“落とし穴”です。
この記事では、実際に起きた事故をもとに、
「なぜ事故は起きたのか?」
「どんな判断ミスがあったのか?」
「何を学ぶべきか?」をひも解いていきます。
自信が引き起こしてしまった事故
トレイルランニングの世界に足を踏み入れた40代の男性ランナーがいた。
彼はマラソン歴10年以上、走力には絶対の自信があり、フルマラソンも何度も完走、年代別では入賞するほどの走力があったそうだ。
ある日、初めて参加したトレイルランの大会で、彼はこれまでのロードでは味わえなかった達成感と自然の中を駆け抜ける快感にすっかり魅了された。
あと少し下りが上手く走れたら、表彰台も夢ではない、、、!?とあたりに話していたようだ。、

それから間もなく、彼は「この感動を誰かと分かち合いたい、もっと練習したい」と考えるようになる。
そして、職場の後輩を誘い、自身が出場したレースのコースを再びたどる形で、練習を兼ねたトレイルランを計画した。
その日は快晴で、2人は気持ちよく山に入った。
先頭を走る彼は、自信に満ちていた。
ところが、途中の分岐でコース取りを誤り、予定外のルートに入ってしまう。
道標も見落とし、いつの間にか整備された登山道から外れ、岩場の多い尾根筋に差しかかった。
この先を見てくると言って先に進んだ彼は、数分しても戻ってこなかった。
不審に思った後輩が後を追うと、10メートルほど先の突き出た岩の下に倒れている姿を発見した。
彼は滑落したようで呼びかけに応答がなかった。

救助要請が行われ、山岳救助隊が駆けつけたが、搬送には多くの時間と人手を要した。
後輩は強いショックを受け、今も山に入れなくなってしまったという。
「経験」と「自信」のギャップ
この事故は、単なる不注意では済まされない。
マラソンでの豊富な経験が、トレイルでも通用するという“錯覚”を生み、自信が慎重さを奪った。
舗装路と違い、山はコースが消えていたり、落石や滑落のリスクが常にある。
レースではマーキングや誘導員がいるが、個人での山行ではすべてを自分で判断しなければならない。
後輩を誘う責任
特に見落とされがちなのが、「人を連れていく」ことの重さだ。
たとえ好意であっても、山での案内役には責任が伴う。
ルート選定、天候判断、体調の変化、何かあったときの救助要請──それら全てを請け負う覚悟がなければ、軽率な誘いは命取りになる。
必要な装備と心構え
この事故では、滑落により即死に近い状態だったというが、そもそも引き返す判断ができていれば防げたかもしれない。
携帯トイレやファーストエイドキット、ヘッドライト、補給食など、最低限の装備は揃っていただろうか。
人を誘ったときに、自分のためだけでなく「もう一人分の安全」を背負える準備があったのか。
問い直すべき点は多い。
「自信」が最も危ない瞬間
初めてのトレイルランで得られる達成感は大きい。
だが、それが
「もう大丈夫だ」
「山を分かった気になった」
という過信につながることも少なくない。
特にマラソンで一定の経験がある人ほど、
その傾向は強い。
山は誰にでも牙をむく場所だ。
ベテランであっても、トップ選手であっても、
判断を誤れば取り返しのつかないことになる。
命を守るのは「謙虚さ」
私たちは、山に挑むとき、
自分の力量を正しく見極めなければならない。
そして、誰かを連れていくときは、
その人の命を預かる覚悟が必要だ。
この事故を通じて、私たちは“自信”という言葉の裏に潜む危うさを知ることになる。
過信を防ぐ唯一の方法は、常に謙虚でいること。
それが、山で命を守る最大の武器である。