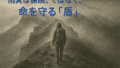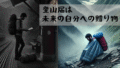「このくらいなら行けるだろう」
「すぐに戻れるから、ちょっと様子を見てみよう」
山の中で、そんな風に考えたことはありませんか?
その「ちょっと」や「なんとなく」という軽い気持ちが、実は帰還への道を閉ざしてしまう、最初の扉かもしれないのです。
今回は、トレイルランナーが陥ってしまった、「なんとなく」という感覚の罠について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
事例:本仁田山で起きた、僅か10数メートルの判断ミス
その事故は、ある初夏の奥多摩・本仁田山で起こりました。
当事者は、2人の女性トレイルランナー。二人とも、レースで入賞するほどの実力者でした。日々のトレーニングとして、その日も慣れたコースを軽快に走っていたのです。
山頂から南に伸びる尾根道。スピードに乗って下る途中、本来であれば急に左へと折れるべき登山道の分岐点がありました。しかし、トレイルランニング特有のスピード感と、前方に「なんとなく行けそう」に見える不明瞭な踏み跡があったことから、二人はその重要な分岐を見落とし、まっすぐ尾根上を進んでしまったのです。
しばらく進むと、次第に道は不明瞭になり、足元の感触も変わってきました。
「あれ…? なんだか道がおかしいね」
二人は立ち止まりました。GPSで現在地を確認すれば、正規の登山道はほんの10数メートル横にあることが分かっていたはずです。今すぐに来た道を引き返せば、何の問題もなく安全なルートに復帰できる距離でした。
しかし、ここで運命を分ける一言が発せられます。
「大丈夫。ちょっとこの先の様子を見てくるから、ここで待ってて」
仲間をその場に残し、一人が尾根の先へと進んでいきました。そのわずか数秒後、静かな森に「キャーッ!」という悲鳴と、岩が崩れ落ちる音が響き渡りました。
仲間が駆けつけると、彼女は落ち葉に隠された急峻な岩場で足を滑らせ、数メートル下に滑落していました。意識はなく、頭からは血が流れていました。仲間はすぐに救助を要請し、電話口の指示に従って、必死に心臓マッサージを始めました。救助隊が到着するまでの2時間近く、彼女は友の胸を押し続けたと言います。しかし、その願いも虚しく、仲間の命が戻ることはありませんでした。
ほんの少し引き返す勇気があれば。
「この先は危ないから、一緒に戻ろう」と声をかけていれば。
あまりにも些細な判断の誤りが、取り返しのつかない悲劇を生んでしまったのです。
なぜ「なんとなく」危険な方へ進んでしまうのか?
この痛ましい事故は、決して他人事ではありません。なぜ経験豊富なランナーでさえ、最も安全な「引き返す」という選択ができず、「様子を見に行く」という危険な行動をとってしまったのでしょうか。そこには、登山やトレイルランニングに潜む、特有の心理的な罠が存在します。
① スピードが「立ち止まる」判断を鈍らせる
特にトレイルランニングのように、ある程度のスピードを維持しながら行動していると、私たちの脳は「前へ進む」ことを前提として働くようになります。思考に慣性がつき、分岐点や標識のような静的な情報を認識しづらくなるのです。視野も狭まり、「あれ?」と違和感を覚えても、「立ち止まって確認する」という行動への心理的なハードルが上がってしまいます。「すぐに気付くだろう」「このまま進んでも大丈夫だろう」という、根拠のない楽観論が生まれやすくなるのです。
② 「行けそう」に見える地形の罠
資料の地図を見ると、事故現場は急な崖ではなく、「丸い尾根」であったことがわかります。これこそが、登山者を誘い込む最も危険な地形の一つです。
明確な崖や、進むのが不可能なほどの藪であれば、誰もが危険を察知して引き返します。しかし、一見すると歩けそうな笹薮、緩やかに下っていく斜面、そして誰かが歩いたような「不明瞭な踏み跡」は、「なんとなく行けそう」という錯覚を生み出します。人間には、困難な道よりも少しでも楽そうな道を選んでしまう本能があります。しかし、山において「楽そうに見える道」や「道ではない踏み跡」は、ほぼ例外なく危険な場所へと続いています。
③ 経験と自信が引き起こす、致命的な油断
この事故が私たちに突きつける最も重要な教訓は、「ベテランだから大丈夫」ということは絶対にない、という事実です。
高い走力、豊富なレース経験、山への慣れ。そうした経験値は、時に「自分は大丈夫」「これくらいの道迷いなら、すぐにリカバリーできる」という過信に繋がることがあります。初心者であれば即座に恐怖を感じて引き返すような場面でも、ベテランは「自分のスキルでなんとかできる」と判断し、よりリスクの高い選択をしてしまうことがあるのです。この「自信」こそが、「来た道を引き返す」という最も安全で確実な選択肢を、後回しにさせてしまう最大の要因となり得るのです。
「おかしい」は、Uターンへの絶対的なサインです
道迷いは、遭難の第一歩です。「なんとなく」という感覚を打ち消し、常に冷静な判断を下すために、以下の掟を心に刻んでください。
CODE 2-6: 「なんとなく行けそう」な道は、道ではない。僅かでも「おかしい」と感じたら、その場で行動を停止し、確実な場所まで引き返すこと。
この掟を実践するために、具体的な行動原則を3つご紹介します。
CODE 1:【原則】道に迷ったら、まず動かない(STOP)。
「あれ?」と感じたら、反射的に動き回るのは最悪の選択です。焦りは判断を狂わせ、状況をさらに悪化させます。まずはその場で行動を停止(Stay)し、一つ深呼吸をしてください。そして冷静に思考(Think)します。コンパスで方角は合っているか? GPSで現在地はどこか? 周りの地形(Observe)と地図を見比べ、ピンクテープや標識などの人工物がないか、注意深く観察します。そして、最も安全で確実なルートに戻るための計画(Plan)を立ててから、初めて行動を再開するのです。
CODE 2:【行動】「様子見」は厳禁。引き返すことに、躊躇は不要です。
「ちょっとこの先の様子を見てくる」という行動は、一見すると合理的に思えるかもしれません。しかし、これは道迷いを遭難へとエスカレートさせる、最も危険な行為です。なぜなら、すでに道ではない危険なエリアに、自らさらに深く足を踏み入れることに他ならないからです。10メートル先が崖かもしれない、深い沢かもしれないのです。どんなに僅かな距離であっても、自分が歩いてきた、安全が確認されている道を正確にトレースして戻ること。これが、リスクをゼロに近づける唯一の解決策です。「10メートル戻る労力を惜しんだ結果、二度と帰れなくなることもある」という事実を、私たちはこの事故から学ばなければなりません。
CODE 3:【心構え】全ての登山者は、道に迷う可能性があると知ること。
「自分は大丈夫」「ベテランだから迷わない」といった考えは、今すぐ捨ててください。初心者もベテランも、人間である以上、誰にでも道に迷う可能性はあります。むしろ、「自分はいつでも道に迷う可能性がある」という謙虚な気持ちで山に臨むことこそが、結果的に安全マージンを大きく広げるのです。こまめに地図を確認するようになり、分岐点に敏感になり、「あれ?」という小さな違和感を決して見過ごさなくなります。その謙虚さこそが、あなたを危険から遠ざけてくれるのです。
一つの判断ミスが、残された仲間や家族にどれほど深い悲しみをもたらすか。残された仲間のことを思うと、言葉になりません。
あなたのその一歩は、本当に「道」の上ですか?
その問いかけを、山の中では常に、心の中で繰り返してください。