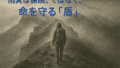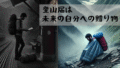「山小屋での楽しいひととき…冷えたビールや仲間との会話は、登山の大きな魅力の一つです。しかし、その後の行動次第では、楽しい思い出が一転、命の危機に繋がる可能性があることを忘れてはいけません」

皆さん、こんにちは。MA-SANです。
今回は、登山における基本的なようで、多くの人が軽視しがちな「食事」と「エネルギー補給」の重要性について、具体的な遭難事例を交えながら解説します。特に、空腹や低血糖が、私たちの判断力をいかに麻痺させ、遭難リスクを高めるのかを理解していただきたいと思います。
事例:深酒と空腹が招いた、50代男性の道迷い遭難
50代の男性Bさんは、長年の登山仲間との恒例行事として、奥多摩の雲取山を目指す山行を計画しました。初日は埼玉県の三峰から入山し、美しい稜線を歩いて雲取山荘に到着。仲間との再会を喜び、夕食時にはついつい話が弾み、お酒も進んでしまいました。普段は節制しているBさんも、山の上という開放感からか、かなりの量の日本酒を飲んでしまったそうです。
夜は案の定、寝つきが悪く、何度も目が覚めます。同室者のいびきも重なり、熟睡できたとは言えませんでした。
翌朝。二日目の行程は、石尾根を経由して鷹巣山を越え、水根沢(みずねさわ)を下って奥多摩湖へ抜ける、長丁場の縦走ルートです。しかし、Bさんは昨夜の深酒が祟り、ひどい二日酔いでした。食欲も全くなく、山小屋で用意された朝食をほとんど口にすることができません。仲間からは「大丈夫か?」と声をかけられましたが、「まあ、歩けばなんとかなるだろう」と、軽い気持ちで出発してしまいました。
出発後も、吐き気と頭痛が治まりません。体は重く、仲間たちのペースについていけません。それでもBさんは、迷惑をかけまいと、懸命に歩き続けます。しかし、鷹巣山を過ぎ、水根沢への下りに入ったあたりで、ついにパーティーから大きく遅れ始めてしまいました。
水根沢のルートは、沢沿いを何度も渡渉する、道迷いのリスクがあるルートです。集中力と判断力が必要とされる場面が続きますが、朝食を抜いてエネルギーが枯渇したBさんの脳は、すでに正常な判断ができない状態でした。
のどの渇きと空腹で、足もふらつく。そんな状態にもかかわらず、Bさんは行動食を摂ろうとしませんでした。「立ち止まるのも面倒だ」「沢を下ればいずれ湖に行き着くだろう」と考えていたのです。これが、致命的な判断ミスでした。
エネルギー不足は、判断力を鈍らせます。通常であれば注意深く確認するはずのルート標識やテープを見落とし、気づかぬうちに彼は正規のルートから外れ、踏み跡の薄い枝沢へと迷い込んでしまったのです。
仲間たちがBさんの異変に気づいたのは、下山予定時刻を過ぎても彼が現れなかった時でした。携帯電話で連絡を取ろうとしましたが、谷間である水根沢に電波が届くはずもありません。心配した仲間たちが山岳救助隊に通報。日も暮れ始め、その日の捜索は困難を極めました。
Bさんが発見されたのは、通報から2日後のことでした。枝沢の奥で、低体温症と脱水症状により、身動きが取れなくなっていました。幸い命に別状はありませんでしたが、深い谷間でたった一人、彼は極度の恐怖と寒さに耐える時間を過ごしたと言います。救助隊員に発見された時、彼は自分がどこにいるのか、どうしてここにいるのかさえ、はっきりと説明できないほど混乱していました。
遭難の分析:低血糖と判断力低下の悪循環
Bさんの遭難は、深酒という最初のきっかけに加え、朝食の欠食、行動食の軽視という、エネルギー管理の失敗が招いた必然的な結果でした。彼の脳は、深刻なエネルギー不足により、正常な機能を完全に失っていたのです。
1. アルコールによる血糖値の乱高下と低血糖リスク
アルコールは、摂取直後は血糖値を上昇させますが、肝臓がアルコールを分解する過程で糖の生成が抑制されるため、その後急激に血糖値を低下させます。特に空腹時に多量摂取すると、低血糖のリスクは著しく高まります。Bさんの場合、深酒に加え、睡眠不足も血糖値の不安定さを助長したと考えられます。
低血糖になると、めまい、ふらつき、冷や汗といった身体的症状に加え、集中力の低下、判断力の鈍化といった認知機能の障害が現れます。山中では、これらが致命的なミスに繋がります。
2. 朝食と行動食の重要性:脳への安定したエネルギー供給
脳の主なエネルギー源はブドウ糖です。安定した思考力と判断力を維持するためには、血中のブドウ糖濃度を一定に保つことが不可欠です。朝食は、睡眠中にエネルギーを使い果たした脳に、一日の活動を始めるための最初のエネルギーを送り込む、非常に重要な食事です。
また、長時間の行動中には、行動食によってブドウ糖を定期的に補給し続ける必要があります。Bさんのようにこれを怠ると、徐々に脳のエネルギーが欠乏し、集中力の低下、ルート選択の誤り、危険察知能力の低下といった症状が現れ、遭難リスクが急激に向上します。
3. ハンガーノックは「思考停止」のサイン
行動食を怠り、エネルギー消費が補給を上回る状態が続くと、体は貯蔵していたグリコーゲンを使い果たし、極度のエネルギー欠乏状態に陥ります。これが、いわゆる「ハンガーノック」です。
ハンガーノックは、強烈な空腹感だけでなく、全身の脱力感、集中力の極端な低下、そして最も危険なのは、合理的な判断力の著しい低下を引き起こします。Bさんのように、ルート選択を誤ったり、今の状況を正しく認識できなくなるのは、ハンガーノックによる「思考停止」が原因である可能性が極めて高いと言えます。
教訓:エネルギー切れから判断力を守るための「THE MOUNTAIN CODE」
エネルギー不足は、合理的な判断力を奪い、遭難への直行路を作り出します。身体だけでなく、精神状態をも危機的に悪化させるエネルギー切れを防ぐための、3つの行動規範です。
CODE 1:山小屋での飲酒は「翌日の自分への投資」と考え、朝食は必ず摂る
山小屋での楽しみは大切ですが、深酒は睡眠の質を低下させ、翌日のパフォーマンスを著しく損ないます。特に翌日に長い行程を控えている場合は、アルコールの量を控えめにしましょう。そして、翌朝は食欲がない場合でも、必ず炭水化物やタンパク質を中心としたエネルギーになる食事を摂ってください。最低でもおにぎりやパン、エネルギーバーなど、すぐに力になるものを口にすることが、自分への最低限の投資です。
CODE 2:行動食は「おやつ」ではなく「命綱」。計画的に摂取する
行動中は、空腹を感じる前にエネルギー補給をするのが鉄則です。すぐにエネルギーに変わる食べ物(チョコレート、ナッツ、ドライフルーツ、エネルギーバー、ジェルなど)を携行し、1時間に一度を目安に少しずつ摂取する習慣をつけましょう。特に長い下りや難しい岩場など、集中力が必要なセクションに入る前には、必ずエネルギーを補給してください。
CODE 3:「ちょっと疲れた」「お腹が空いた」は、判断力低下の危険信号
「まだ大丈夫」と根性で乗り切ろうとせず、少しでも疲労感や空腹感を感じたら、それは脳がエネルギー不足に陥りかけているサインです。すぐに安全な場所で休憩し、エネルギー補給を行いましょう。特に地図の確認やルート選択など、判断を伴う行動の前には、必ず体と脳にエネルギーが満たされている状態で行うように心がけてください。「まあ、なんとかなるだろう」という油断が、最悪の結果を招くことを忘れてはいけません。
山は、美しい景色と冒険を与えてくれますが、同時に厳しい環境でもあります。その環境の中で安全に楽しむためには、自身の体の状態を正確に把握し、適切なタイミングでエネルギーを補給することが不可欠です。
エネルギーを意識的に管理し、常に合理的な判断力を維持する。それこそが、山で安全に過ごすための、最も基本的な原則です。